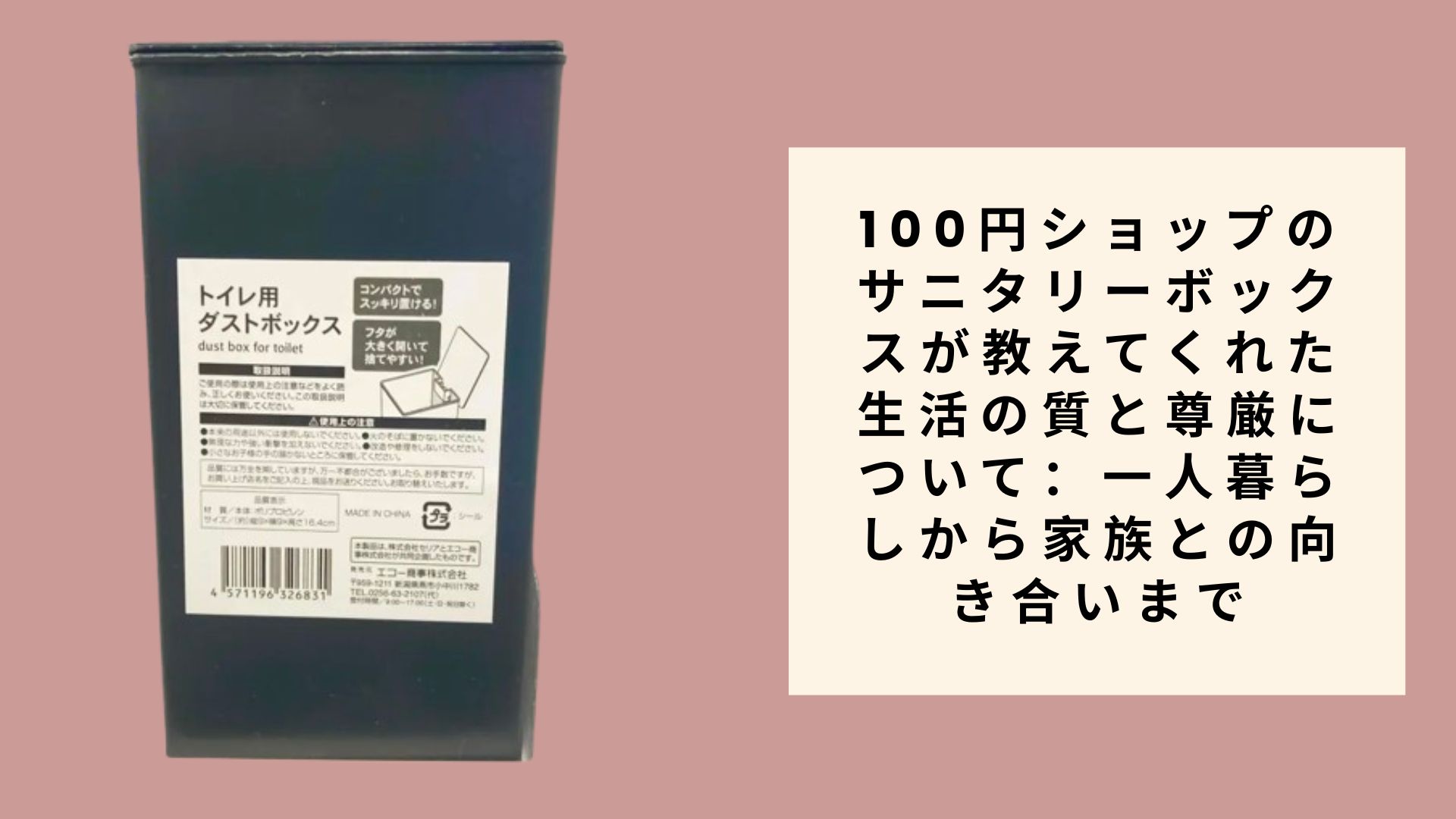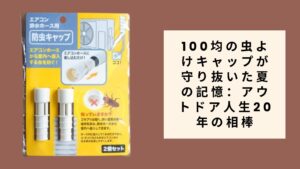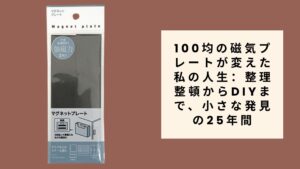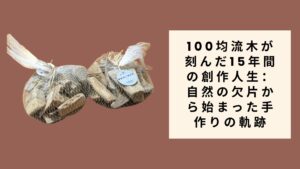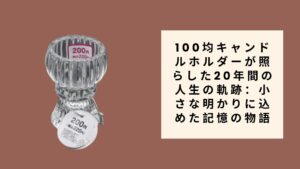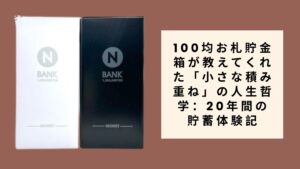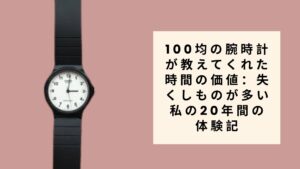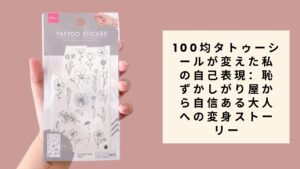実家で両親と暮らしていた頃、サニタリーボックスの存在を意識したことは一度もありませんでした。トイレの片隅にごく自然に置かれていて、それが母によって定期的に清潔に管理されていることも、当時の私には「当たり前」すぎて気に留めることもありませんでした。
生理用品の処理についても、母が用意してくれた環境の中で、何の不便も感じずに過ごしていました。「こういうものはどこにでもある」「必要な時には必ずそこにある」という前提で生活していたのです。
振り返ってみれば、母は私が初潮を迎えた時から、娘が快適に過ごせるように様々な配慮をしてくれていました。しかし、当時の私にはその配慮の深さや、母の細やかな気遣いに気づく余裕もありませんでした。
無意識の安心感: 実家のトイレには常に清潔なサニタリーボックスがあり、それが私に安心感を与えてくれていたことを、後になって理解しました。
母の見えない努力: 母が定期的に中身を処理し、消臭剤を交換し、清潔を保ってくれていたことを、その時は全く意識していませんでした。
当たり前への甘え: 「あって当然」という環境で育った私は、それがなくなった時の不便さを想像することもできませんでした。
一人暮らし開始と現実の壁
大学進学を機に始めた一人暮らし。新しいアパートに引っ越して初めて、「サニタリーボックスがない」という現実に直面しました。引っ越し準備の際にも、カーテンや寝具、食器などは思い浮かんだのに、サニタリーボックスのことは完全に頭から抜け落ちていました。
生理が始まった時、いつものようにトイレに入ると、片隅に「いつものもの」がありません。その瞬間、これまで当たり前だと思っていたものが、実は「誰かが用意してくれていたもの」だったのだと初めて気づきました。
焦りとパニック: 生理用品をどう処理すればいいのか、一人暮らしを始めてから初めて真剣に考えることになりました。
応急処置の限界: とりあえずビニール袋に包んで燃えるゴミに出しましたが、これで良いのか確信が持てませんでした。
恥ずかしさと孤独感: 誰に相談すれば良いのかわからず、こんな基本的なことを知らない自分が恥ずかしく感じました。
実家への感謝: この時初めて、母がしてくれていたことの大きさを実感しました。
友人との会話で知った多様な現実
数日後、大学の友人たちとの何気ない会話の中で、サニタリーボックスの話題が出ました。みんな一人暮らしを始めたばかりで、同じような問題に直面していることがわかりました。
友人A(裕福な家庭出身)は「無印良品でおしゃれなのを買った」と言い、友人B(実用重視)は「ホームセンターで一番安いのを探した」と話していました。一方で、友人C(経済的に余裕がない)は「まだ買えてない、どうしよう」と困っていました。
価格への驚き: 友人たちが話していた価格を聞いて、サニタリーボックスがこんなに高価なものだとは知りませんでした。数千円という金額は、生活費を切り詰めている大学生には決して安くない出費でした。
デザインへのこだわり: 友人Aが見せてくれた写真は確かにおしゃれでしたが、「機能は同じなのに、なぜこんなに値段が違うの?」という疑問も湧きました。
経済格差の現実: 友人Cの状況を見て、生活必需品すら買えない学生がいることを知り、複雑な気持ちになりました。
100円ショップでの発見と決断
友人たちとの会話を受けて、まずはホームセンターに向かいました。確かに様々なサニタリーボックスが売られていましたが、一番安いものでも2000円近くしました。デザインは素敵でしたが、生活費をやりくりしている身としては、簡単に手が出せる金額ではありませんでした。
「もう少し安いものはないかな」と思いながら帰り道、いつも利用している100円ショップに立ち寄ってみることにしました。日用品コーナーを見回していると、「サニタリーボックス」と書かれた商品を発見しました。
シンプルな白いプラスチック製で、蓋付きの小さなゴミ箱のような形をしていました。デザインは確かに高級品と比べると質素でしたが、機能的には十分に思えました。何より、110円という価格は私の予算にぴったりでした。
迷いと決断: 「安すぎて品質が悪いのでは?」という不安もありましたが、「まず試してみよう」と購入を決めました。
罪悪感: なぜか「こんな安いものを買って良いのだろうか」という罪悪感もありました。生理用品の処理は、もっと「きちんとした」ものでするべきなのではないかという思い込みがあったのです。
期待と不安: 家に帰る道中、「本当に使えるのかな」という不安と、「これで問題が解決する」という期待が入り混じっていました。
実際の使用と予想外の満足感
家に帰って早速開封してみました。作りは確かにシンプルでしたが、蓋もしっかりと閉まり、内側も滑らかで清掃しやすそうでした。トイレの片隅に置いてみると、サイズもちょうど良く、目立ちすぎることもありませんでした。
実際に使い始めてみると、機能面では高価なものと何も変わりがないことがわかりました。蓋があることで臭いも気にならず、処理も簡単でした。「100円でこの品質なら十分すぎる」というのが正直な感想でした。
清掃の簡単さ: プラスチック製なので水洗いが可能で、清潔を保つのも簡単でした。
サイズの適切さ: 一人暮らしの狭いトイレにちょうど良いサイズで、邪魔になることもありませんでした。
蓋の機能: しっかりと閉まる蓋により、臭いや見た目の問題も解決されました。
コストパフォーマンス: 110円でこの機能が得られることに、正直驚きました。
生活の質向上と精神的な安定
サニタリーボックスを設置してから、生理期間の過ごし方が大きく変わりました。それまでは生理が始まるたびに「処理はどうしよう」という小さなストレスを感じていましたが、それが完全になくなりました。
精神的な安定: 「いつでも適切に処理できる」という安心感は、想像以上に大きなものでした。
来客時の安心: 友人が遊びに来た時も、「もしもの時」の備えがあることで、お互いに安心して過ごせるようになりました。
自立感の向上: 小さなことですが、「自分で生活環境を整えることができた」という達成感がありました。
母への感謝: 改めて、母がこれまでしてくれていたことへの感謝の気持ちが深まりました。
友人たちへの情報共有と反響
100円ショップのサニタリーボックスの使い心地が良かったため、経済的に困っていた友人Cに教えてあげることにしました。彼女も早速購入し、「こんな良いものがあるなんて知らなかった!」と大変喜んでくれました。
この話は他の友人たちの間でも話題になりました。高価なものを購入した友人Aも、「機能は同じなのに、なぜあんなに高いものを買ったんだろう」と笑っていました。
情報格差の実感: 「良い商品の情報」にもアクセスのしやすさに差があることを実感しました。
価格と価値の関係: 必ずしも高価なものが良いわけではないということを、身をもって学びました。
仲間との絆: 共通の悩みを解決できたことで、友人たちとの絆も深まったように感じました。
アルバイト先での体験と社会問題への気づき
大学2年生になってから始めたカフェのアルバイトで、女性用トイレの清掃も担当するようになりました。その時に初めて、「サニタリーボックスがない職場」の存在を知ることになりました。
私が働いていたカフェは個人経営の小さな店で、オーナーは男性でした。女性用トイレにサニタリーボックスが設置されていないことを指摘すると、「え、そんなものが必要なの?」という反応でした。
男性の理解不足: 男性にとって生理は体験できないことであり、必要性を理解してもらうのがいかに困難かを実感しました。オーナーは悪意があるわけではなく、単純に「知らなかった」のです。
働く女性の困難: 女性スタッフは私を含めて3人いましたが、みんな困っていることを我慢していました。「言い出しにくい」という雰囲気があったのです。
社会的な問題: 個人の問題だと思っていたことが、実は社会全体の理解不足という大きな問題の一部だということに気づきました。
声を上げる勇気: 最終的に私がオーナーに提案し、100円ショップのサニタリーボックスを職場にも設置してもらうことができました。
卒業論文での研究テーマに
この体験がきっかけで、大学の卒業論文のテーマを「公共空間における女性の生理用品処理環境」に設定することにしました。図書館や駅、学校などの公共施設でのサニタリーボックス設置状況を調査し、女性の社会参加との関係を研究することにしたのです。
調査の実施: 市内の公共施設50箇所を実際に訪問し、設置状況を調査しました。
意外な結果: 設置率は予想以上に低く、特に古い建物では皆無に近い状況でした。
利用者の声: アンケート調査では、多くの女性が「困った経験がある」と答えていました。
経済的側面: 管理者側の「コストがかかる」という懸念も、調査で明らかになりました。
100円商品の可能性: 私の研究では、100円ショップの商品を活用することで、低コストでの環境整備が可能であることも提案しました。
就職と職場環境への意識
大学卒業後、IT企業に就職することになりました。面接の際、何気なく女性用トイレを確認したところ、きちんとサニタリーボックスが設置されていることに安心感を覚えました。この時点で、私にとってサニタリーボックスの有無は「その組織の女性への配慮レベルを測る指標」になっていました。
入社後、総務部に配属された私は、オフィス環境の整備も担当することになりました。その中で、女性用トイレの備品管理も私の仕事の一部となりました。
コスト意識: 会社の備品として購入する場合、やはりコストは重要な要素でした。100円ショップの商品の品質を知っていた私は、迷わずそれを提案しました。
上司の反応: 男性の上司からは「そんなに安いもので大丈夫なの?」という心配の声もありましたが、実際に使ってもらうことで理解を得ることができました。
女性社員からの評価: 他の女性社員からは「きちんと管理されていて安心」という声をもらい、職場環境への満足度向上につながりました。
コスト削減効果: 年間のコストを計算すると、従来品と比べて大幅な削減効果があることがわかりました。
結婚と夫への教育的体験
5年後、大学時代から付き合っていた彼と結婚することになりました。同棲を始める際、新居にサニタリーボックスを設置することについて話し合いました。彼は「そういうものが必要なんだ」ということを理解してくれましたが、具体的にどういうものかは知りませんでした。
一緒に100円ショップに買い物に行った時、私がサニタリーボックスを手に取ると、彼は「これがそうなの?こんなにシンプルなものなんだ」と驚いていました。
男性の素直な疑問: 「なぜ専用のものが必要なの?普通のゴミ箱じゃダメなの?」という彼の質問に、蓋の重要性や衛生面について説明しました。
理解と協力: 説明すると素直に理解してくれ、「そういうことなら、きちんとしたものを用意しよう」と言ってくれました。
価格への驚き: 100円で購入できることに、彼も驚いていました。「高価なものだと思っていた」そうです。
設置後の気遣い: 設置後は、来客時に「女性の方も安心して使えるよ」と自然に声をかけてくれるようになりました。
妊娠・出産期の体験変化
結婚3年目に妊娠し、つわりの時期を経て出産を迎えました。この期間は、サニタリーボックスとの関係も変化しました。
つわり期間中: 臭いに敏感になり、今まで気にならなかったサニタリーボックスの臭いも気になるようになりました。100円商品でも蓋がしっかりしているおかげで、大きな問題はありませんでした。
産後の使用: 出産後の悪露の処理で、久しぶりにサニタリーボックスの重要性を実感しました。産後の体調が不安定な中、信頼できる処理方法があることの安心感は大きなものでした。
来客への配慮: 産後の来客が増える中で、女性の友人や姉妹が安心して過ごせる環境を提供できていることに満足感を覚えました。
経済的メリットの再確認: 出産費用など大きな支出がある中で、日常用品のコストを抑えられていることの価値を改めて感じました。
娘への生理教育と継承
娘が10歳になった頃から、生理についての話をするようになりました。私自身が母から受けた教育を振り返り、より良い形で知識を伝えたいと考えていました。
環境整備の重要性: 娘に生理について説明する際、「適切な処理環境を整えることの大切さ」も一緒に教えました。
経済観念の教育: 「必要なものを適切な価格で購入する判断力」についても話しました。100円ショップの商品を例に、「価格と品質のバランスを見極めること」の重要性を伝えました。
社会問題としての認識: 私が大学で研究したことを踏まえ、「個人的な問題だと思っていることが、実は社会的な問題でもあること」を教えました。
男性への説明スキル: 将来パートナーができた時に、きちんと説明できるコミュニケーション能力の大切さも伝えました。
地域での啓発活動
娘のPTA活動をきっかけに、学校環境の改善についても関わるようになりました。古い校舎の女子トイレにサニタリーボックスが設置されていない問題を発見し、改善提案を行いました。
学校側の事情: 予算の制約や管理の手間を懸念する声もありましたが、100円ショップの商品を活用することで低コストでの解決策を提示しました。
保護者の反応: 提案に対して多くの母親から賛同の声をもらい、父親からも「知らなかった」という驚きの声が多く聞かれました。
実現への道のり: 最終的に学校側も理解を示し、必要な箇所に設置してもらうことができました。
継続的な管理: 設置後の管理についても保護者が協力する体制を作り、持続可能な運用を実現しました。
職場での後輩指導
管理職になってからは、新入社員の研修も担当するようになりました。女性の新入社員には、職場環境について質問しやすい雰囲気作りを心がけています。
環境整備の説明: 入社時のオリエンテーションで、女性用設備について説明し、何か不便があれば遠慮なく相談するよう伝えています。
男性社員への教育: 男性の新入社員や管理職に対しても、ダイバーシティの観点から女性が働きやすい環境整備の重要性を説明しています。
継続的改善: 定期的に女性社員にヒアリングを行い、環境改善に努めています。小さなことでも積み重ねることで、働きやすさが向上することを実感しています。
100円という価格が持つ意味の深い理解
長年使い続けてきて、100円ショップのサニタリーボックスが持つ意味の深さを理解するようになりました。それは単に「安いから良い」ということではなく、「必要なものを必要な人が手に入れやすい価格で提供する」という社会的価値があるということです。
アクセシビリティ: 経済的な理由で必要なものを我慢する必要がない価格設定の重要性。
機能の十分さ: 高価なものと変わらない基本機能を持っていることの価値。
心理的ハードル: 「試しに買ってみる」ことができる価格であることの意味。
社会的包摂: すべての女性が尊厳を保って生活できる環境作りへの貢献。