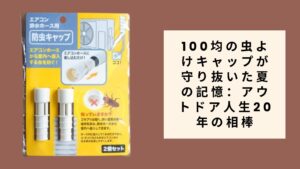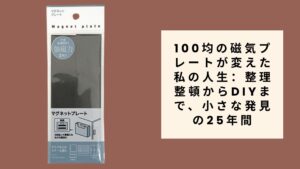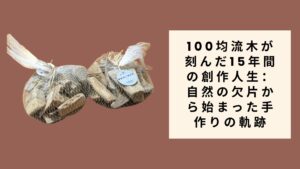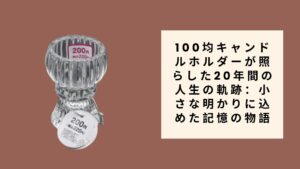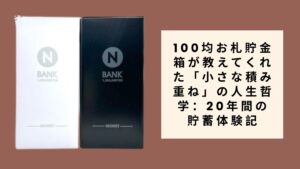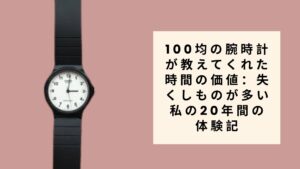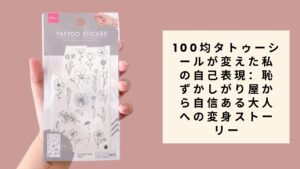私の読書に対する苦手意識は、小学生の頃から始まっていました。同級生が夢中になって本を読んでいる姿を横目に、私はどうしても集中して文字を追うことができませんでした。読書感想文の宿題は毎回苦痛で、あらすじをネットで調べて適当に書いて済ませることが常でした。
中学・高校時代も状況は変わらず、国語の成績は常に最下位クラス。現代文の授業では、先生が「この作品の素晴らしさ」について熱弁をふるっても、私にはただの文字の羅列にしか見えませんでした。「私には読書の才能がないんだ」と完全に諦めていました。
大学受験の際も、参考書を読むことすら苦痛で、結果的に偏差値の低い大学にしか合格できませんでした。「もっと本が読めていれば、人生は違ったかもしれない」という後悔は、心の奥にずっと残り続けていました。
社会人になってからの読書コンプレックス
社会人になると、読書への劣等感はさらに強くなりました。同僚たちが昼休みに小説を読んでいたり、ビジネス書について議論していたりする様子を見て、「大人として恥ずかしい」という気持ちが募りました。
上司から「この本、参考になるから読んでみて」と勧められた時は、特に辛かったです。200ページ程度のビジネス書でも、途中で眠くなったり、内容が頭に入ってこなかったりして、結局最後まで読み切れませんでした。
会議での発言力不足: 読書量の不足は、語彙力や表現力の乏しさにも繋がり、会議での発言にも自信が持てませんでした。
昇進への影響: 管理職になるためには幅広い知識が必要でしたが、読書ができない私は常に情報不足を感じていました。
人間関係への影響: 読書好きの人との会話についていけず、人間関係も狭くなりがちでした。
首・肩の痛みという物理的な問題
30代半ばになって、ようやく読書の必要性を強く感じるようになりました。娘が小学生になり、「お母さんも本を読んで」とせがまれるようになったことがきっかけでした。
重い腰を上げて本を読もうとしましたが、今度は新たな問題に直面しました。本を読んでいると、10分もしないうちに首や肩が痛くなってしまうのです。
下を向く姿勢の辛さ: 本を膝の上に置いて読むと、どうしても下を向く姿勢になり、首に負担がかかりました。
手の疲労: 本を持ち上げて読もうとすると、今度は腕や手首が疲れてしまいました。
集中力の散漫: 体の痛みが気になって、内容に集中できませんでした。
「やっぱり私には読書は無理なんだ」と、再び諦めかけていました。
整形外科での診断と医師からのアドバイス
首の痛みがひどくなったため、整形外科を受診しました。レントゲンを撮った結果、「ストレートネック」と診断されました。
医師からは「デスクワークが多い現代人に増えている症状です。読書の際も姿勢に気を付けてください」とアドバイスされました。「本を読む時は、できるだけ目線を下げずに済む工夫をしてみてください」という言葉が印象的でした。
しかし、具体的にどうすれば良いのかわからず、結局読書からは遠ざかったままでした。
100円ショップでの偶然の発見
ある土曜日の午後、娘の学用品を買いに近所の100円ショップに出かけました。文房具コーナーで娘が必要なものを選んでいる間、私は何気なく店内をぶらぶらと歩き回っていました。
キッチン用品のコーナーを通りかかった時、「ブックスタンド」という商品が目に入りました。パッケージには「読書台」「角度調整可能」という文字が書かれていました。
「まさか100円で読書台が買えるの?」と驚きながら、パッケージの説明を読んでみました。プラスチック製のシンプルな構造でしたが、角度調整ができて、本やタブレットを立てかけられるとのことでした。
整形外科医の「目線を下げずに」という言葉を思い出し、「110円なら試してみても損はない」と思い、購入することにしました。
初めての使用とその驚くべき効果
家に帰って早速、読書台を組み立ててみました。組み立てと言っても、プラスチックのパーツを組み合わせるだけの簡単なものでした。角度は3段階に調整でき、最も立てた状態にすると、確かに目線をあまり下げずに本を読むことができました。
試しに、以前途中で挫折したビジネス書を読書台に立てかけてみました。すると、驚くべきことが起こりました。
首への負担軽減: これまでのような首の痛みを全く感じませんでした。
手の自由: 本を持つ必要がないため、手が自由になり、メモを取りながら読むこともできました。
集中力の向上: 体の痛みがないため、内容に集中できるようになりました。
最初は半信半疑でしたが、30分、1時間と読み続けても疲れを感じません。「これは革命的だ!」と心の中で叫びました。
読書習慣の劇的な変化
読書台を使い始めてから、私の読書に対する意識は180度変わりました。これまで「辛い」「疲れる」という負の感情しかなかった読書が、「楽しい」「もっと知りたい」という正の感情に変わったのです。
毎日の読書時間: 最初は1日15分から始めて、1週間後には30分、1ヶ月後には1時間の読書が習慣になっていました。
読書場所の多様化: リビングのテーブル、ダイニング、さらには和室の座卓でも読書台を使えるため、場所を選ばずに読書できるようになりました。
ジャンルの拡大: ビジネス書から始まり、小説、エッセイ、実用書と、読むジャンルも徐々に広がっていきました。
家族からの驚きと支援
私の変化に最も驚いたのは家族でした。
娘の反応: 「お母さんが本を読んでる!」と最初は驚いていた娘も、今では一緒に読書タイムを楽しむようになりました。娘も小さな読書台を欲しがり、一緒に100円ショップに買いに行きました。
夫の変化: 夫も私の読書習慣に影響を受け、自分用の読書台を購入しました。夫婦で同じ本を読んで感想を話し合うという、新しいコミュニケーションが生まれました。
母からの評価: 読書嫌いだった私を知る母は「人は変われるものなのね」と感慨深そうに言ってくれました。
職場での評価向上
読書習慣が身についてから、職場での評価も徐々に上がっていきました。
語彙力の向上: 読書によって語彙力が向上し、会議でのプレゼンテーションや報告書の質が格段に良くなりました。
知識の幅広さ: 様々なジャンルの本を読むことで、話題の幅が広がり、同僚との会話も弾むようになりました。
問題解決能力: ビジネス書や実用書から得た知識を実務に活かせるようになり、上司からも「最近頼もしくなった」と評価されました。
昇進: 読書を始めて2年後、ついに念願だった主任昇格が実現しました。面接で読書について質問された時、自信を持って答えることができました。
読書環境の最適化
100均の読書台で読書の楽しさを知った私は、より快適な読書環境を整えることにしました。
照明の改善: デスクライトを購入し、読書台と組み合わせることで、夜でも目に負担をかけずに読書できるようになりました。
クッションの活用: 長時間の読書では腰も疲れるため、背もたれクッションを併用するようになりました。
読書記録: 読んだ本の記録をつけるようになり、年間の読書目標を設定するようになりました。
複数台の活用: 家の各所に読書台を置くようになり、リビング用、寝室用、職場用と使い分けるようになりました。
年間読書目標の達成
読書台を使い始めて1年目、私は25冊の本を読み切ることができました。これまでの人生で読んだ本の総数を上回る数字でした。
2年目には50冊、3年目にはついに年間100冊を達成しました。「私が年間100冊?」と自分でも信じられませんでしたが、読書記録を見返すと確確かに100冊読破していました。
ジャンル別内訳: ビジネス書30冊、小説25冊、エッセイ20冊、実用書15冊、その他10冊という構成でした。
印象に残った本: 特に感動したのは村上春樹の「ノルウェイの森」で、これまで「小説は難しい」と思っていた私でも、読書台のおかげで最後まで集中して読むことができました。
知識の蓄積: 読書ノートに記録した名言や学んだことは、500ページを超えていました。これらの知識が日常生活や仕事で活かされることが増えました。
読書会への参加と新たなコミュニティ
年間100冊を達成したことで自信がついた私は、地域の読書会に参加することにしました。最初は「私なんかが参加して大丈夫だろうか」と不安でしたが、読書台で培った読書習慣が支えてくれました。
初参加の緊張: 読書会初日は手が震えるほど緊張しましたが、他の参加者も様々なレベルの人がいることがわかり、安心しました。
ディスカッションの楽しさ: 同じ本を読んでも、人によって解釈が全く違うことに驚きました。「読書は個人的な行為だと思っていたが、実は対話的な活動なんだ」ということを学びました。
新しい友人関係: 読書を通じて年齢も職業も異なる友人ができました。月1回の読書会が待ち遠しくなりました。
課題図書への挑戦: 読書会の課題図書には、自分では選ばないような難しい本も含まれていましたが、読書台があることで集中して読み切ることができました。
娘の教育への好影響
私の読書習慣は、娘の教育にも大きな影響を与えました。
親子読書タイム: 毎晩30分の親子読書タイムを設けるようになりました。娘は児童書、私は大人の本をそれぞれの読書台で読む時間です。
読解力の向上: 娘の国語の成績が格段に向上しました。担任の先生からも「家庭での読書習慣の効果が表れています」と褒められました。
読書感想文の共同作業: 娘の夏休みの読書感想文も、一緒に本を読んで話し合いながら書けるようになりました。私自身が読書感想文で苦労した経験があるため、娘には同じ思いをさせたくありませんでした。
図書館通い: 親子で図書館に通う習慣もできました。娘が本を選んでいる間、私も新しい本を物色する楽しい時間です。
健康面での意外な効果
読書台を使った読書習慣は、思わぬ健康効果ももたらしました。
姿勢の改善: 正しい姿勢で読書する習慣がついたことで、日常生活の姿勢も改善されました。整形外科の定期検診で、「ストレートネックが改善している」と医師に驚かれました。
集中力の向上: 読書によって集中力が鍛えられ、仕事の効率も向上しました。以前は2時間かかっていた資料作成が、1時間半で完了するようになりました。
ストレス軽減: 読書が良いストレス発散になり、イライラすることが減りました。特に小説を読んでいる時は、日常の悩みを忘れて別の世界に没入できました。
睡眠の質向上: 就寝前の読書習慣により、スマートフォンを見る時間が減り、睡眠の質が向上しました。
読書台のカスタマイズと工夫
長期間使用する中で、100均の読書台をより使いやすくする工夫を編み出しました。
滑り止めの追加: 読書台の底面に滑り止めシートを貼ることで、机の上で安定性が向上しました。
角度調整の改良: 3段階の角度調整では物足りなくなり、小さなクッションを挟むことで微調整できるようにしました。
ページめくり問題の解決: 風でページがめくれてしまう問題は、小さな洗濯バサミで解決しました。
持ち運び用バッグ: 折りたたみ式の読書台を持ち運ぶための専用バッグを作り、カフェや図書館でも使えるようにしました。
電子書籍との併用
読書習慣が確立してから、電子書籍も試してみることにしました。読書台はタブレット用としても使用できるため、紙の本と電子書籍の両方を楽しめるようになりました。
場所を選ばない読書: 電子書籍と読書台の組み合わせにより、旅行先でも快適に読書できるようになりました。
文字サイズの調整: 目が疲れやすい小説も、文字サイズを大きくして読書台で読むことで、長時間の読書が可能になりました。
検索機能の活用: ビジネス書では、電子書籍の検索機能と読書台の快適性を組み合わせることで、効率的な学習ができました。
コストパフォーマンス: 電子書籍の割引セールを活用することで、年間100冊読んでも書籍代を抑えることができました。
読書指導者としての活動
年間100冊の読書実績と、活字嫌いから読書好きになった経験を評価され、地域の図書館で読書指導のボランティアをすることになりました。
子ども向け読書教室: 読書が苦手な子どもたちに、正しい姿勢での読書の重要性を教えました。100均の読書台を紹介すると、保護者の方々から大変好評でした。
大人向けセミナー: 「読書習慣の身につけ方」というテーマで大人向けのセミナーも開催しました。私の体験談を交えながら、読書環境の整備について話しました。
読書相談: 「本を読みたいけど集中できない」という相談を多く受けるようになりました。その度に読書台の効果を説明し、多くの人に試してもらいました。
職場での読書文化普及
私の読書習慣は職場でも注目され、会社の福利厚生として読書推進活動を始めることになりました。
読書奨励制度: 月1冊の読書レポート提出で図書券がもらえる制度を提案し、実現しました。
オフィス読書スペース: 休憩室に読書コーナーを設置し、そこに読書台も常備しました。昼休みに読書する同僚が増えました。
ブックレビュー会: 月1回、読んだ本の感想を共有する会を開催するようになりました。部署を超えたコミュニケーションも生まれました。
読書を通じた自己啓発
年間100冊の読書は、私の人生観そのものを変えました。
視野の拡大: 様々な著者の考えに触れることで、物事を多角的に見ることができるようになりました。
批判的思考力: ただ本を読むだけでなく、内容を批判的に検討する力も身につきました。
表現力の向上: 読書によって語彙力が向上し、自分の考えをより正確に表現できるようになりました。
継続力の獲得: 読書習慣を通じて、物事を継続する力が身につきました。この力は他の分野でも発揮されています。
読書台コレクションの拡大
100均の読書台の素晴らしさを実感した私は、用途別に複数の読書台を使い分けるようになりました。
リビング用: 家族と一緒にいる時間でも読書できるよう、リビングテーブル専用の読書台。
寝室用: 就寝前の読書専用。角度を緩めに設定し、リラックスした姿勢で読めるもの。
職場用: 昼休みの読書用。コンパクトに折りたためるタイプ。
外出用: カフェや図書館で使用。軽量で持ち運びしやすいもの。
勉強用: 資格試験の参考書を読む時用。メモを取りやすい角度に調整されたもの。
すべて100円ショップで購入したものですが、それぞれが私の読書生活を支える大切なアイテムになっています。
読書仲間とのネットワーク拡大
読書会への参加をきっかけに、読書好きのネットワークが大きく広がりました。
オンライン読書会: コロナ禍をきっかけに始まったオンライン読書会にも参加するようになり、全国の読書好きと交流できるようになりました。
読書ブログ: 自分の読書体験をブログで発信し始めました。「100均読書台で人生が変わった話」という記事は多くの人に読まれました。
SNSでの情報交換: Twitter で読書アカウントを作成し、おすすめの本や読書台活用法について情報交換しています。
読書イベントの企画: 地域で読書関連のイベントを企画・運営するようになりました。